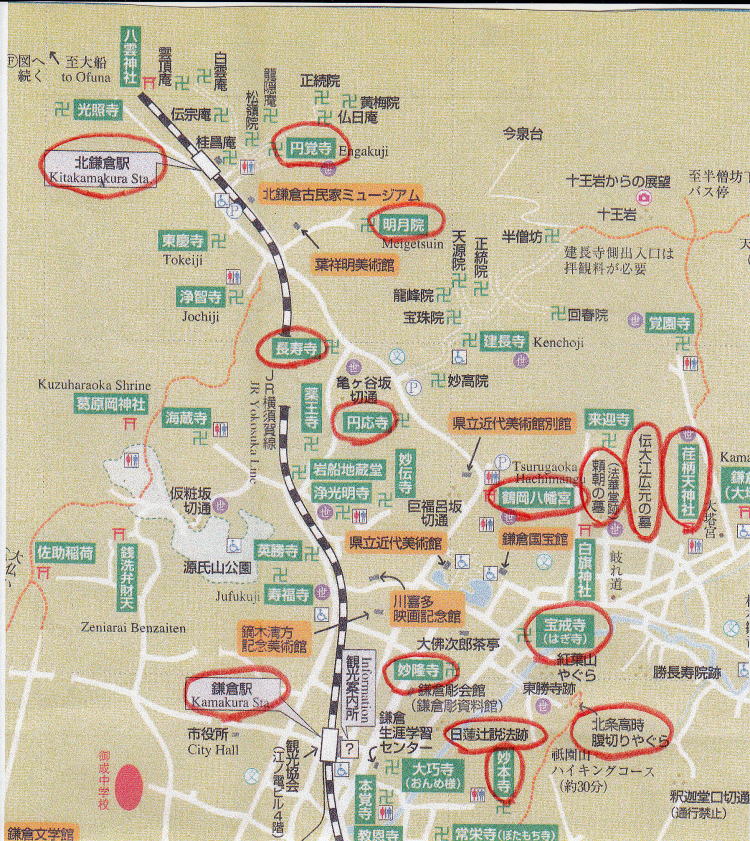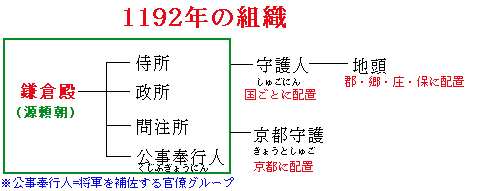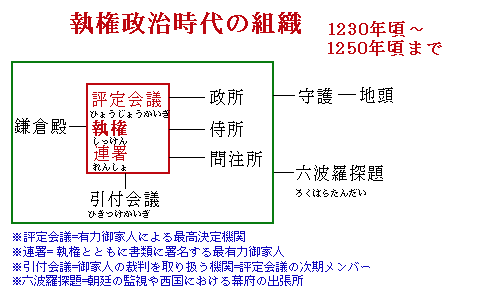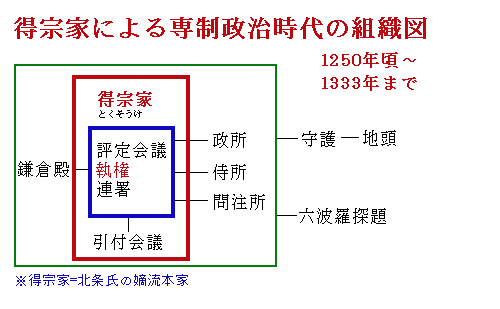|
東慶寺
宗派・・臨済宗円覚寺派 山号寺号・・松岡山東慶総持禅寺 創建・・弘安八年(1285年) 開山・・覚山志道尼 開基・・北條貞時 本尊・・釈迦如来
寺宝・・木造聖観音立像(大平寺重文)・木造水月観音半迦像(県重文)・初音蒔絵火取母(国重文)・葡萄蒔絵螺鈿聖餅箱(国重文)・縁切り関係他古文書(国重文)他
北條時宗の室堀内殿(安達義景の娘)は、時宗が三十四歳で他界すると、仏光国師に師事し出家して法名滝音院覚山志道尼となり、息子の貞時を開基として当寺を創建し自ら開山となった。そして九代執権であった貞時を動かして後宇多天皇から「縁切寺法」の勅許を得た。
寺の住持は一世の志道尼以降四世まで皆北條一門の後室であった。五世の用堂尼は後醍醐天皇の皇女で、この五世の時に「縁切法」が改正され、駆け込んだ女性の寺の在住期間が、三年間から二年間に短縮された。
(松岡御所)十六世~十八世は足利公方の娘が勤め、二十世には豊臣秀頼の娘で千姫の養女天秀法泰尼が入り、その後ろ盾により近世的な「縁切法」が確立された。以上に見られるように寺格が非常に高い寺で、江戸時代寺領は鎌倉で鶴岡八幡宮,円覚寺に次建長寺より多かった。
また江戸時代には、街道に面して六間✕三間の松岡役所があって、寺所属の役人が詰めていて、背後には役宅や吟味所も設けられていた。駆け込みの女性が夫の先回りなどで入寺を阻まれても、下駄や草履等の外櫛・笄など身につけていたものを、門内に投げ入れれば入寺したものと見なされた。駆け込み女が入寺すると役人の取調べがあり、寺から飛脚で夫の呼び出しがあり、吟味の結果和解することもあるが、しない場合は二年後再び夫が呼ばれ離縁状を書かされ、離婚が成立することになっていた。(追加知識の離縁状参照)
縁切寺で知名な寺は東慶寺の外、上野世田の満徳寺が有名である。明治になって縁切法は廃止され、明治三十六年東慶寺は尼寺でなくなったが、この寺には有名人の墓が多数ある。数例を揚げると西田幾太郎・岩波茂雄・阿倍能成・和辻哲郎・鈴木大拙・高見順・太田瑞穂・田村俊子・小林秀雄・佐々木房・前田青邨(筆塚)・大松博文・・・・
この寺には四季を通じて花があるが、特に春の梅は観梅の客でにぎわう。
代表的な花・・紅梅・白梅・黄梅・花桃・マンサク・イワタバコ・ヤマボウシ・桜・彼岸花・菖蒲・白木蓮・・・・
|


|
明月院
宗派・・臨済宗建長寺派 山号・・福源山 明月庵・・永暦元年(1160年) 禅興寺・・文永五年(1268年)
開山・・密室守厳 開基・・上杉憲方 本尊・・聖観世音菩薩
明月院は平治の乱で戦死した父の霊を弔うため、山ノ内経俊が建てた明月庵が起源で、北條時頼が1256年この地に最明寺を建立し、時頼の没後時宗がこの最明寺を前身として禅興寺(開山 蘭渓道隆)を創建した。その後足利氏満の命を受けた上杉憲方が、寺域を拡大し塔頭も建てゝ中興した。この時明月庵は明月院と改められ支院の首位に置かれた。上杉憲方の法名(明月院大樹道合)はこの明月院から来ている、三代将軍足利義満の時代に、禅興寺は関東十刹の一位となるが、明治初年に廃寺となり支院の明月院だけが残った。紫陽殿(本堂)には本尊が、その左手の宗猷堂(仏殿)には密室守厳像が安置されている。鎌倉十井の一つ「瓶ノ井」・憲方の墓・時頼の墓などが見ものである。
アジサイ寺で有名だが四季折々花が咲いている。
主な花・・ロウバイ・シダレ桜・レンギョウ・ボケ・モモ・モミジ・水仙・ツバキ
北條時頼の頌
業鏡高懸三十七年 一槌打砕大道坦然 (弘長三年十一月二十二日)
|

|
長寿寺 宗派・・臨済宗建長寺派 山号・・宝亀山 創建・・元享三年(1323年)~延元元年(1336年) 開山・・古先印元(伝) 開基・・足利基氏 本尊・・観音菩薩
境内は非公開
この寺は初代鎌倉公方足利基氏が、父尊氏の屋敷跡にその菩提を弔うために建立したといわれている。寺の名は尊氏の法名・長寿殿から名付られた。かっては伽藍や塔頭を備えた寺院であったらしいが、今は山門・仏殿・庫裏などがあるだけである。境内奥のやぐらには基氏が父尊氏の遺髪を埋めたと伝えられる五輪塔がある。 茶会などがよく開かれているようで、頼めば精進料理をたべさせてくれるようである。 |

|
第六天社
第六天神社は建長寺の四方鎮守の南の位置を占める社である。東・西・北の鎮守があったと思われるが不明である。建長寺境内図(延宝六年・1678年)には、四方鎮守第六天と記されており、天保二年(1831年)改築の棟札には、創建は宝永四年(1707年)とある。社殿内には第六天像が中心に祀られ、前列には四天王像が安置されている。第六天は仏教では他化自在天と称し、魔王のごとき力を持つといわれ、神道では第六天即ち第六番目の神と認識されている。神奈川県内には第六天を祀る社が180以上有り、厄除けや方位の神として信仰されている。この第六天はまた上町の氏神様でもあり、昨年国の史跡指定を受けた。例祭は毎年七月十五日~二十二日に行われている。 |

|
円応寺
宗派・・臨済宗建長寺派 山号・寺号・・新居山円応寺 創建・・建長2年(1250年)
開山・・智覚禅師 本尊・・閻魔王
この寺は閻魔堂や十王堂とも言われる。昔は荒居閻魔堂といわれ由比郷見越岩にあったものを、足利尊氏が由比の鶴岡郷に移したが、元禄16年(1703年)の地震や津波で流されて現在の位置に移された。境内には本堂・庫裏・鐘楼がこじんまり収まっている。本堂には本尊の閻魔大王(伝運慶作)を中心に、冥土の世界で死者の裁判をする秦広王・初江王・宋帝王・伍官王・変成王・太山王・平等王・都市王・伍道転輪王などの十王と奪衣婆(県重文)などの木像が並んでいる。亡者は七日毎に裁きを受け、百日目に平等王、一年目に都市王、三年目に伍道王に裁かれてようやく判決が出る。これが十王思想であり、地蔵信仰と共に鎌倉時代から広く信仰されて来た。十王のうち初江王(国重文)は、具生像・鬼卒像(県重文)・人頭杖(県重文)などと共に、鎌倉国宝館に展示されている。
見所・・・閻魔大王像(笑い閻魔) 各木像
アメリカノウゼンカズラ キンモクセイ ロウバイ
|

|
鶴岡八幡宮二十五坊跡
「碑文」 鶴岡八幡宮二十五御坊舊蹟
此の地ハ頼朝時代以来 八幡宮供僧ノ僧舎二十五坊及別当坊ノ置カレシ処ナリ 彼ノ別当公暁ガ實朝ノ首ヲ手ニシテ潜ミタル 後見 備中阿闍利ノ宅モ亦此ノ地ニ在リタルナリ 応永中(1394~1428)院宣ニヨリ坊ノ称ヲ院ト改ム戦国ノ世ニ至リ鎌倉管領ノ衰微ト共ニ各院次第ニ廃絶シ 天正ノ末(1592)ニ於イテハ僅ニ七院ヲ存セルノミ 文禄中(159~1596)徳川家康五院ヲ再興シテ十二院トナセルガ 明治維新後遂ニ全ク廃壚ナレリ
大正七年三月建之 鎌倉町青年会
|

|
稲瀬川石碑
「碑文」
稲瀬川碑文
萬葉ニ鎌倉ノ美奈能瀬河トアルハ 此ノ河ナリ 治承四年(1180)十月政子鎌倉ニ入ラントシテ來リ 日並ノ都合ニヨリ數日ノ間此ノ河辺ノ民家ニ逗留セル事アリ 頼朝ガ元暦九年(正しくは元暦元年1184)範頼ノ出陣ヲ見送リタルモ 正治元年(正しくは文治元年1185)義朝ノ遺骨ヲ出迎ヘタルモ共ニ此ノ河辺ナリ 元弘三年(1333)新田義貞ガ寄手ノ大将大館宗氏ノ此ノ河辺ニ討死セルモ人ノ知ル所 細キ流ニモ之ニ結バル物語少ナカラザルナリ
大正六年三月建之 鎌倉町青年会
|

|
大太刀稲荷社
言い伝えでは、新田義貞の鎌倉攻めの合戦の時、刀を取り落とした武将が、現れた白い狐に守られたということで、その武将は攻め手の大将大館宗氏ではないかと言われている。
この神社は市内に七つある御嶽社の一つで、太刀持ち稲荷の外いろいろな石碑がある。
|

|
御霊神社(権五郎神社) 祭神は通説では鎌倉権五郎と言われている。御霊神社というのは土地の神として、祖先を祀る神社のことで各地にある。
桓武天皇の子孫平義兼の孫村岡五郎忠通に五人の息子があり忠通の死後五家に分かれ、夫々が栄えるように忠通と五家の先祖を祀り、御霊の神とか五霊の神として祀って来たともいわれている。後に権五郎景正が祀られるようになった。
権五郎は、後三年の役に十六歳で源義家に従い活躍した武将で飛びぬけた武勇の持ち主だったこと、このあたりの領地を開いたことなどによると思われる。
面掛行列・・・権五郎景正の命日に行われる祭りで、県の無形民俗文化財になっている。爺・ひょっとこ・福禄寿・おかめ・鬼・鼻長・異形・翁・烏天狗・女と十の仮面(伎楽・舞楽に用いるような)をつけて、神輿の前を練り歩く。福禄寿があることからこの神社は鎌倉七福神の一つになっている。(祭礼は九月十八日)
|

|
星月夜の井 鎌倉十井の一つで星月ノ井・星ノ井ともいう。
この辺りは、昔昼なお暗く山深い所で、この井戸の中を覗くと昼でも星が輝いて見えたことから、この名がついたと言われている。
また近くの女の人が井戸水を汲む時に、包丁を落としてしまったところ、以後星は輝かなくなったとも伝えられている。
昔の旅人が極楽寺坂を越えて来て、一休みするには貴重な井戸水であったらしい。
鎌倉十井・・・瓶ノ井・甘露ノ井・底脱ノ井・扇ノ井・泉ノ井・鉄ノ井・棟立ノ井・銚子ノ井・六角ノ井・ 星月夜ノ井
「星月井碑文」
星月夜ノ井ハ一ニ星ノ井ヨモ云ウ 鎌倉十井ノ一ナリ 坂ノ下ニ属ス 往時此ノ附近ノ地老樹翁鬱トシテ昼尚暗シ 故ニ星月谷ト曰フ 後転ジテ星月夜トナル 井名蓋シ此二基ク 里老言ウ 古昔此井中昼モ星ノ影見ユ 故ニ此ノ名あり 近傍ノ卑女誤ツテ菜刀ヲ落セシヨリ以來 星影復タ見エザルニ至ルト 此説最モ里人ノ為ニ信ゼラレルガ如シ慶長五年(1600)六月 徳川家康京師ヨリノ帰途 鎌倉ニ過リ特ニ此井ヲ見タルコトアリ 以テ其名世ニ著ハルルヲ知ルベシ 水質清冽最モ口ニ可ナリ
昭和二年三月建 鎌倉町青年団
|

|
虚空蔵堂 天平年間、行基が回国の際ここで虚空蔵を祭る修法を行ったところ、星月夜の井戸に三つの明星が現れた、井戸水を汲み上げると不思議な形の石であった。行基はこれは、虚空蔵さまを祭れというお告げだと思い、明鏡山円満院星井寺を建てた。元禄年間に再建されたが関東大震災で壊滅した。
虚空蔵菩薩・・・知恵と福徳の仏様。一般には十三仏の最後三十三回忌の本尊として又丑と寅年生まれの人の守り本尊、更に十三詣りの本尊とされている。虚空蔵菩薩は知恵と福徳を無限に内蔵しており、衆生の願いを叶えるために蔵から自在に取り出して救済する。密教の大日如来の働きのうち「虚空」と「蔵」という特性を持った菩薩で、虚空は何ものにも打ち破れない無能勝であり、蔵は全ての人々に利益・安楽を与える宝を収めている蔵という意味である。
十三詣り・・・京大阪では子供が13歳になった時にお詣りするのを十三詣りといゝ、十三詣りは京都の法輪寺が有名で、虚空蔵菩薩から知恵と厄除け授けていただくと、授かった知恵と厄除けが戻ってしまわないように、渡月橋を渡り終えるまで後を振り返ってはいけないと言われている。
十三仏・・・初七日─不動明王、二十七日─釈迦如来、三十七日─文殊菩薩、四十七日─普賢菩薩、五十七日─地蔵菩薩、六十七日─弥勒菩薩、七十七日─薬師如来、百ヶ日─観世音菩薩、一周忌─勢至菩薩、三回忌─阿弥陀如来、七回忌─阿閦如来、十三回忌─大日如来、三十三回忌─虚空蔵菩薩
|

|
極楽寺切通
往時の道は今の成就院の高さくらいで傾斜が急な幅も狭いものだった。七切通しの一つで、こゝから七里ヶ浜を通って藤沢に通じる道であり、都と鎌倉を結ぶ重要な出入り口であった。北條重時が晩年この土地に極楽寺を建てゝここに住んだのは、鎌倉を守るため政治的・軍略的必要からであった。
新田義貞の鎌倉攻めの時はこゝは固く閉ざされ雌雄を決する古戦場となった。攻める側は大館宗氏を大将とする、その数十万ともいわれる兵で攻めかかり、一時は北條方が敗れたが直ぐに押し返し大館一族は討ち死にしてしまう。(十一人塚)新田義貞はこゝの守りが堅いのを見て稲村ガ崎に回ったのである。
鎌倉七切通・・・巨福呂坂切通 亀ヶ谷切通 化粧坂切通 名越切通 朝比奈切通 大仏切通 極楽寺切通
極楽寺坂切通碑文
此所往古畳山ナリシヲ 極楽寺開山忍性菩薩 疎鑿シテ一条ノ路ヲ開シト云ウ 即チ極楽寺切通ト唱フルハ是ナリ 元弘三年(1333)鎌倉入ニ際シ 大館次郎宗氏江田三郎行義ハ新田軍ノ大将トシテ此便路ニ向ヒ 大佛陸奥守貞直ハ鎌倉軍ノ大将トシテ此所ヲ堅メ相戦フ 昭和七年三月建 鎌倉町青年団
|

|
成就院
宗派・・真言宗大覚寺派 山号・寺号・・普明山法立寺 創建・・承久元年(1219年)
開山・・弘法大師 開基・・北條泰時 本尊・・不動明王 こゝは弘法大師が諸国巡礼の折、数日の間虚空蔵菩薩を祭る修法を行った所と伝えられている。承久元年三代執権泰時がこの切通に、鎌倉の守りのためと北條氏の繁栄を祈ってこの寺を建てた。元弘三年の鎌倉攻めで焼失、江戸時代に再建された。本尊の外に千手観音,大日如来,地蔵菩薩,弘法大師像,文覚上人荒行の像などが安置されている。
明月院と並んでアジサイの寺として有名な寺である。
|

|
上杉憲方の墓 多層塔が憲方の墓、五層塔が憲方の妻の墓といわれ、市の文化財になっている。
憲方は山ノ内上杉氏の出で、二代鎌倉公方足利氏満に仕えて関東管領を勤めた人で、晩年は出家して道合と言い山ノ内の明月院を開いた人である。
坂道の反対側の人家の裏の山際に六つの五輪塔と永和五年(1379年)の銘がある宝篋印塔が並んでいる。
この辺りは、極楽寺内にあった塔頭の一つ西方寺の跡と言われていてこの宝篋印塔は憲方の供養のため、妻が生前に建てた逆修塔と言われている。
|


|
極楽寺
宗派・・真言律宗 山号・・霊鷲山感応院 開山・・忍性菩薩 開基・・北條重時
創建・・正元元年(1259年) 本尊・・釈迦如来
真言律宗は釈迦在世中の教えを守り、仏の示したきまりや教えを厳しく行い、生活の上にそれを実践することで、仏に近ずけると考える真言宗の一派。重時は寺の完成を待たず世を去るが、その子長時・業時が力を合わせて継続し完成時には、七堂伽藍・四十九院を備えた大寺院であった。寺に伝わる古絵図に二重屋根の金堂、十三重の塔など沢山の塔が建つ様子が壮大に描かれている。
鎌倉攻めの戦いで寺は焼けたり壊れたりし、その後何度かの火災・地震・大風などで崩れ落ち、今は唯一つ残っている吉祥院が本堂になっているだけで、当時の広い境内の大部分は稲村ガ崎小学校や住宅地帯に変わってしまっている。
忍性上人(菩薩)・・・真言律宗を開いた叡尊の弟子で早くから布教を助け、釈迦の教えを説くことに活躍した。厳しい修行をしながら仏の道を実践するために、困った人を救うことを考え、施薬院・悲田院・療養院などを建て、盛んに社会福祉事業をおこなった。20年間に6万人の世話をしたと言われている。
極楽寺の墓地が少し離れた裏山の麓に有り、そこに良寛房忍性の墓がある。民衆に慕われ、時の執権北條時頼・時宗の帰依を受け死後に後醍醐天皇から菩薩の号を贈られた忍性に相応しい高さ約4メートルの重厚な五輪塔の墓である。
|

|

|
阿仏尼邸旧蹟
阿仏尼は鎌倉時代の歌人で右衛門佐といった。藤原定家の子爲家の継室となり、爲相を生んだ。爲家の死後出家して、阿仏または北林禅尼といった。嫡男爲氏と実子爲相との所領争いから、阿仏尼が訴訟のために鎌倉に下った。その時の紀行文が十六夜日記である。裁きの間約4年間この月影ヶ谷に住んだといわれる。
阿佛邸舊蹟碑文
阿佛ハ藤原定家ノ子為家の室ニシテ和歌ノ師範家冷泉家ノ祖為相ノ母ナリ為相ノ異母兄為氏 為相ニ属スベキ和歌所ン0所領 播磨細川庄ヲ横領セルヲ以テ之ヲ執権時宗ニ訴ヘ其ノ裁決ヲ乞ハントシ 建治三年(1277)京ヲ出デテ東ニ下リ 居ヲ月影ガ谷ニトス即チ此ノ地ナリ其ノ折ノ日記ヲ十六夜日記ト云ヒテ世ニ知ラル 係争久シキニ彌リテ決セズ 弘安四年(1281)遂ニ此ニ没ス 大正九年三月建之 鎌倉町青年会
句碑には「月影の谷若葉して道清し」と刻まれている。
|

|
針磨橋
鎌倉十橋の一つで、昔此の附近に針を磨く老婆が住んでいたとか、極楽寺の塔頭に住んでいた我入道というお坊さんが、針を磨いていたとかいわれている。海岸の近くに金山という地名があったことや、海岸に砂鉄の多い砂があることから、鉄製品の原料供給の一部になっていたと思われる。(正宗の名刀?)
鎌倉十橋・・・十王堂橋・勝の橋・裁許橋・琵琶橋・夷堂橋・歌の橋・筋替橋・逆川橋・乱レ橋・針磨橋
針磨橋碑文
鎌倉十橋ノ一ツニシテ 往昔此ノ附近ニ針磨ヲ業トセシ者住ミニケリトテ 此ノ名アリトイフ 昭和三年三月建 鎌倉町青年団
|

|
日蓮袈裟掛の松
日蓮が文永八年(1271年)竜ノ口の刑場へ連れて行かれるとき、「いかに汚れた世の中とはいえ、この尊いお袈裟を血で汚すのは恐れ多い」といって脱ぎ、おしいただいて松の下枝に掛けて行ったということである。松は何代も植え継がれ周囲も整備され今に至っている。
|

|
十一人塚
元弘三年(1333年)鎌倉攻めの時大館宗氏は新田軍の浜手の大将となり、大軍を率いて極楽寺坂の切通へ攻め込み、切通を突破して御霊神社のあたりから、由比ガ浜の方へ展開しようとしたが、北條方の新手の猛攻撃に会い最後まで残った十一共々討ち死にしたといわれる。それで此処に十一人を葬り、十一面観音の像を建てゝその霊を弔ったので「十一人塚」といわれている。
碑文
元弘三年(1333)五月十九日 新田勢大館次郎宗氏ヲ大将トシテ極楽寺口ニ攻入ラントセシニ 敵中 本間山城左衛門手兵ヲ率イテ大館ノ本陣ニ斬込ミ為ニ宗氏主従十一人戦死セリ 即遺骸ヲ茲ニ埋メ 十一面観音ノ像ヲ建テ以テ其ノ英魂ヲ弔シ之ヲ十一人塚ト称セシト云ウ
昭和六年三月 鎌倉町青年団
|

|
新田義貞と稲村ケ崎
極楽寺方面から山が海岸まで押し出している岬の形が、稲束を積み上げたような形をしていることから稲村ケ崎といわれるようになった。往時は軍勢を通すような道は無く、波飛沫を避けながらやっと通れる危険な小道があったようである。新田義貞は極楽寺切通からの攻撃は無理だと判断し、海岸線を突破しようと考えた。しかし道は無く海上には大船がぎっしりと守りを固めており、こゝも隙がないように見えた。「義貞は皆を集め大願成就を海神に祈り腰にさした黄金造りの太刀を海に投げ入れた。するとその願いが届いたのか、月が沈む頃稲村ケ崎の海が俄かに引き、数千の兵船は遥か沖に押し流されてしまった。こを見て新田勢は干潟を渡って鎌倉に乱入した。」(太平記─11頁参照)
稲村ケ崎は、かって霊仙山と地つずきであったが、134号線のため切断され、海辺に残された島のようになってしまった。
この公園には、稲村ケ崎新田義貞徒渉伝説地の碑・明治天皇の歌碑・逗子開成中学生のボート遭難碑・コッホ博士の記念碑などがある。
碑文
今ヲ距ル五百八十四年ノ昔 元弘三年(1333)五月二十一日 新田義貞此ノ岬ヲ廻リテ鎌倉ニ進入セントシ 金装ノ刀ヲ海ニ投ジテ 潮ヲ退ケンコトヲ海神ニ祈レリト言フハ此ノ処ナリ
大正六年三月建之 鎌倉町青年会
太平記
そして五月二十二日、新田義貞の最終的鎌倉総攻撃が敢行された。「太平記」は、次のように記している。(鎌倉史蹟事典より)
義貞馬ヨリ下給テ、甲ヲ脱デ海上ヲ遥々ト伏拝ミ龍神ニ向テ祈誓シ給ケル。 仰願ハ内海外海ノ龍神八部、臣ガ忠義ヲ鍳テ、潮ヲ万里ノ外ニ退ケ、道ヲ三軍ノ陣ニ令開給ヘト 、至信ニ祈念シ、自ラ佩 給ヘル金作ノ太刀ヲ抜テ、海中ヘ投給ケリ。真ニ龍神納受セ シ給ケン、 其夜ノ月ノ入方ニ、前々更二干ル事モ無リケル稲村崎、俄ニ二十余町干上テ、平沙渺々タリ。横 矢射ント構ヌ ル数千ノ兵船モ、遥ノ澳ニ漂ヘリ。不思議ト云モ無類。
|